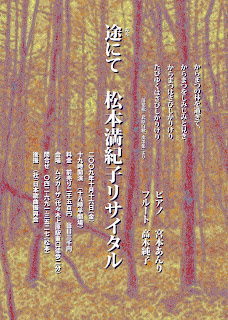エレクトーンシティには、9時半入りです。到着すると、すでに大谷歩さん、清道洋一さん、田中修一さん、仁科拓也さん、宮﨑文香さん、三河修三さんが来ていました。中川博正さんとは、来る途中で会いました。調律の方は、8時から来て作業をしています。トロッタのために、人が動いているわけです。
楽屋に荷物を運び込み、10時の音出しを待ちます。待つといっても、することはいろいろあります。何といっても、私は差し替え曲になった『宇の言葉〜七角星雲・光うた・火の山〜』を告知するため、原稿を作らなければなりません。また、アンケートも作る必要があります。寝てしまって作業をしなかったのですが、寝ることは必要なので、私はかまいません。その皺寄せが、後で押し寄せるわけです。しかし、自分の練習時間以外にすれば間に合うという計算が働いていることは事実です。
10時から10時30分 エレクトーンの音出しに続いて、橘川琢さんの『宇の言葉~七角星雲・光うた・火の山~』を合わせる時間です。エレクトーンの音が、なかなかうまく出ないように見えました。トロッタはまだ、エレクトーンを自分のものにできていないなと思いました。もちろん、大谷歩さんに不安はありません。かつて、私はビデオ作品を作っていました。ビデオは電気に左右されます。もし、停電になったら……。それは妙な仮定です。停電になったら、室内で行われる演奏会そのものが中止になるでしょう。ともかく、電気に左右される表現を、私はやめました。エレクトーンはまさしく、ビデオと似ています。しかし、今回のトロッタは、エレクトーンを使うことが大前提です。作曲者にとっても出演者にとっても、ひとつの挑戦となったのです。
『宇の言葉』は、昨夜、池袋駅でもらっただけの楽譜です。自分の詩ですが、間違えずに詠めるでしょうか。いえ、間違えてもいいから、心の詩唱になるでしょうか。考えまして、私が前に正座することにしました。ヴァイオリンの戸塚ふみ代さんには、私の真後ろに立って、演奏していただくことにしました。
10時30分から10時50分 戸塚さんと、バンドネオンの生水敬一朗さんによる『Venus』です。曲は、生水さんの先生、アレハンドロ・バルレッタ氏によるものです。本番一曲目のシャンソン組曲もそうですが、出演者が歌いたい曲、演奏したい曲に取り組んでいただきたいと思い、プログラムに加えたのです。
10時50分から11時30分 橘川琢さんの『花骸-はなむくろ-』です。花の上野雄次さんが、どんなことをするのか、この時点ではまだわかりません。また、私が出す山蛭の声が、客席にどんな効果となって聴こえるかもわかりません。聴こえているようではありますが。戸塚さんのヴァイオリン、田中千晴さんのフルート、中川さんの声、すべてを聴きながら、深い山の中の光景を作っていきます。
11時30分から11時50分 田中修一さんの『ムーヴメント』です。赤羽佐東子さんの生の声が、赤羽さんが無理をしなくとも、客席に届くかどうか。打楽器、ピアノ、エレクトーンが大音量で演奏されます。もともと響きのない会場です。人工リバーブ装置に頼るしかありません。私が赤羽さんの歌を初めて聴いたのは、このエレクトーンシティで行われた日本歌曲の会でした。ピアノの森川あづささんと打楽器の星華子さんは、高校時代の同級生です。私とシャンソンの笠原千恵美さんもそうですが。個人的には、そのような人と人の歴史が、私は好きです。
11時50時から12時20分 大谷歩さんの『アルバ』です。大谷さんは、この一週間、山口から出てきて、知らない人ばかりの中に混じり、よく努力されたと思います。私自身、電話やメールでやりとりしていましたが、面識はありません。大谷さんが山口から出てきた日に、初めて会いました。『アルバ』で私が詩に詠んだ海は、大谷さんが見ていた海です。つまり、同じ瀬戸内海です。互いの共通項が、音になるわけです。これは不満ではなく、当然、そうなっていいわけですが、詩は、ずいぶん短くなっています。どこをどう取って曲にするか。その作曲家の判断に、私は関心があります。
12時20分から13時00分 これも海にまつわる曲、清道洋一さんの『アルメイダ』です。この日のために、清道さんは小松史明さんと、一枚の絵を作りあげました。そこには私の原詩が載っています。演奏に使われるテキストは、戯曲のようなものと私には映る、清道さんの創作です。実はこの二つの詩の関係が、いまひとつ、わかっていません。わからないまま本番に臨むのは不誠実かもしれません。しかし、その不安感が、私の声を通して形作られる、一人の男の姿には、ふさわしい気もします。結局、この音楽劇のような『アルメイダ』は、何なのでしょうか? 清道さんの思いを、どこかで語っていただきたい気がします。加えて、赤羽佐東子さんが歌う、女王のアリアを、より大きくした形で、私の原詩の長さで、聴きたいと思っています。
13時00分から13時半 今井重幸先生の『青峰悠映』です。田中千晴さんのフルート、平昌子さんのファゴット、大谷歩さんのエレクトーンで演奏されます。サントリーホールの小ホールで聴かせていただいた曲を、トロッタで演奏させていただけます。ありがたいことです。また、田中さんと平さんは、大学のオーケストラで共演していましたが、外に出て共演するのは初めての機会だとか。いいことだと思います。練習を聴きながら、私は差し替え曲の告知とアンケートを作りました。
13時半から14時 やはり今井先生が曲を書き、橘川氏と清道氏が編曲をした、“シャンソン組曲”。邦題で、「今井重幸によるヌーベル・シャンソン 新しい歌の流れ」です。ここで問題が生じ、音が厚すぎるために歌がまったく聴こえない事態となりました。急遽、検討をしまして、マイクを使うことにしました。トロッタでは、本来、ありえないことです。これもまた、試行錯誤です。試行錯誤をお聴き、見せてしまうわけです。いいのでしょうか。いいわけはありません。全員の努力を、よりよい形にまとめてゆく力が、不足していました。
14時から『めぐりあい』を合わせました。大谷さんのエレクトーンと、弦楽カルテットのみの演奏で、他の人は歌います。アンコール曲である『めぐりあい』まで、無事に持っていけるかどうか。非常な不安を抱えたまま、開場の時間が迫ります。詩唱者として、個人的には不安はないのです。トロッタとしての不安です。さらに、こうして書いている今、すでに終わったことなのに、その綱渡りぶりが不安になってきました。よく、終えられたと思います。
14時半 開場です。さまざまな反省を生ぜしめたトロッタ9が、始ります。この後のことは、公開されたことであり、書きません。ほめていただいた点もありますが、批判された点も多く、お客様が大勢お越しにならなかったことが、すでにトロッタへの批判かもしれません。トロッタ10は、絶対に、9以上のお客様を集めること。曲の差し替えやマイクの使用などをせずに済むこと、その他、さまざまな課題をクリアいたします。そのために、すでに動き出しています。